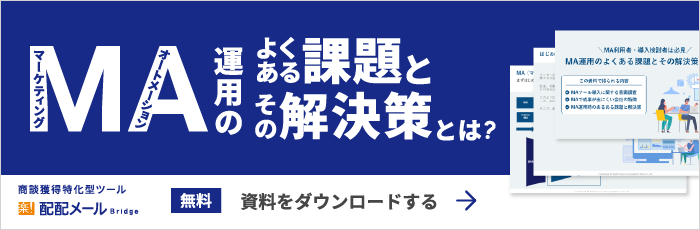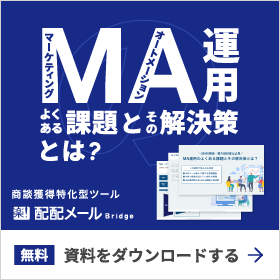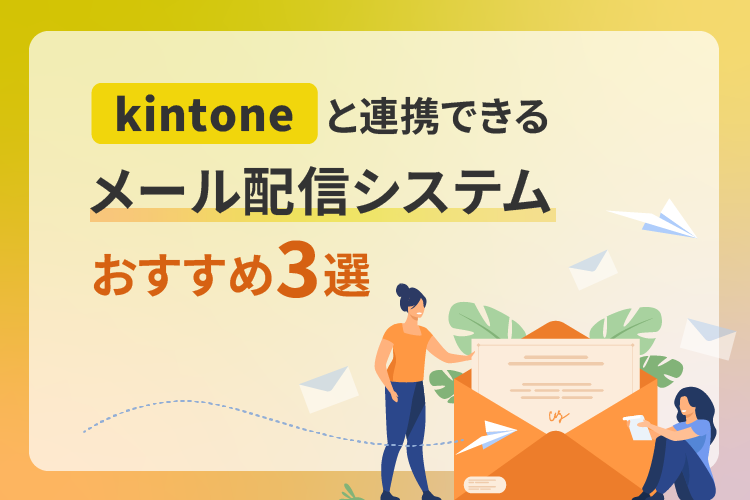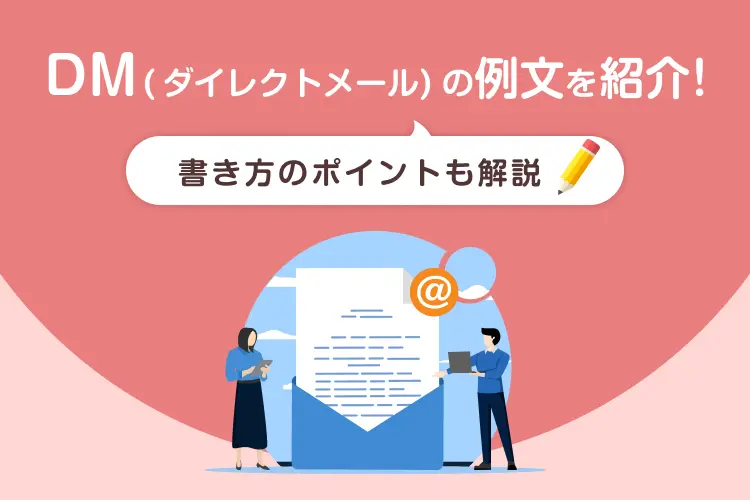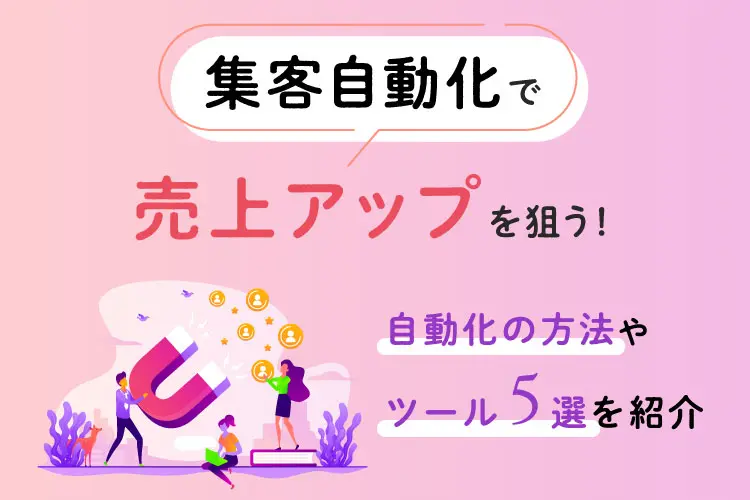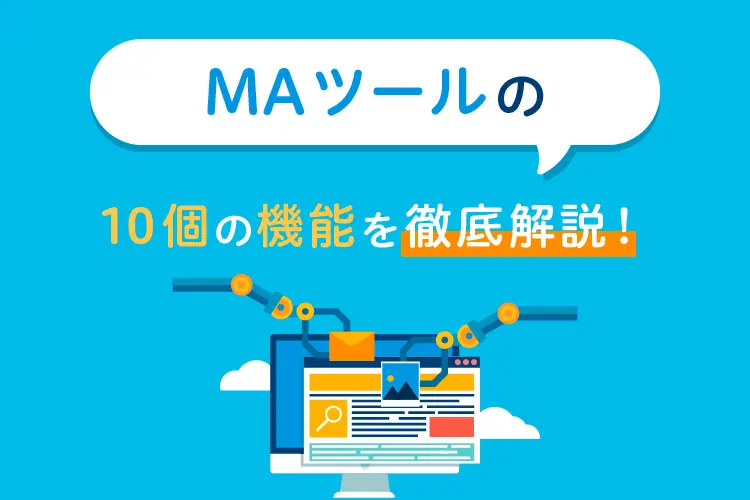オウンドメディア運営のポイントは?BtoB企業の成功事例や失敗例を交えて解説
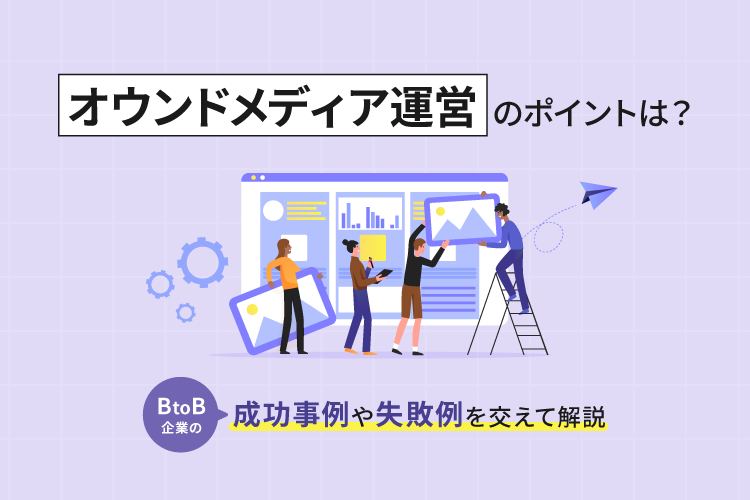
BtoB企業におけるオウンドメディアの運営は、今やマーケティング活動の中核を成す戦略的アプローチとして位置付けられています。かつては展示会への出展や営業活動が中心だったBtoBマーケティングですが、デジタル技術の進化と顧客の購買行動の変化に伴い、オウンドメディアが重要な役割を果たすようになりました。特に、顧客が自身で情報を検索し意思決定を行うプロセスが一般化する中で、企業が自ら情報を発信し、顧客との接点を増やすことの重要性が高まっています。
しかしながら、オウンドメディアの運営には計画的な取り組みが不可欠であり、成功の鍵を握るのは戦略的な運用です。本記事では、BtoB企業がオウンドメディアを運営する際のポイントについて、メリット・デメリット、具体的な成功事例などをご紹介します。
目次
BtoB企業がオウンドメディアを運営するメリット
BtoB企業にとって、オウンドメディアの運営はマーケティング活動の中でも非常に大きな役割を果たします。近年、顧客の購買行動がデジタルを起点とする形へとシフトしており、企業が直接情報を発信できるメディアの重要性が増しています。これにより、見込み客の獲得や認知度の向上、ブランド力の構築が可能となり、企業にとって多大な価値を生み出します。
以下では、BtoB企業がオウンドメディアを運営する具体的なメリットについて、6つのポイントに分けて詳細に説明します。
見込み客が獲得できる
オウンドメディアの最も大きな魅力のひとつは、見込み客を効率的に獲得できる点にあります。特にSEO対策を活用すれば、自社の製品やサービスに関連するキーワードを検索する顧客に対して、適切なタイミングで情報を届けられます。たとえば、製造業界で特定の部品調達に関する課題を抱える企業が「部品コスト削減方法」といった検索を行った際、該当するオウンドメディアの記事にアクセスすれば、顧客と企業が接点を持つ機会が生まれるのです。
さらに、オウンドメディアにおけるコンテンツは、一度公開されると長期間にわたり価値を提供できます。これにより、企業は新規顧客を継続的に獲得できる体制を構築しやすくなるでしょう。従来の広告型のアプローチでは、予算を投下している間だけ効果が見込まれるのに対し、オウンドメディアではストック型の集客が可能です。その結果、長期的に安定したリードジェネレーションを実現します。
認知を拡大できる
オウンドメディアを運営するもうひとつの大きなメリットは、企業の認知度を向上させる点です。特にBtoB企業では、一般消費者向けの商品を取り扱う企業とは異なり、対象となる市場や顧客層が限定的なケースが多くあります。そのため、ターゲット層に対して的確な情報を届ける手段としてオウンドメディアが効果を発揮します。
SEOを活用したキーワード選定や、業界特化型の記事を発信すれば、検索エンジン上での可視性が向上します。たとえば、「サプライチェーン効率化」「IoT活用事例」といった具体的なテーマで記事を作成すれば、該当する分野のニーズを持つ潜在顧客が自然に集まる仕組みを構築可能です。このようなプロセスを通じて、企業の存在感を市場に対して確立し、認知度を高められるでしょう。
また、認知度向上の効果は、一過性のものではありません。定期的な情報発信を行い、業界内でのポジショニングを強化すれば、企業は特定分野の専門家としての地位を築き、信頼を獲得できます。このような取り組みは、競合との差別化を図る上でも非常に有効です。
絞り込んだターゲットと接点が持てる
BtoBのマーケティングにおいては、見込み客をできるだけ具体的に絞り込んだ上で効果的なアプローチを行うことが成功の鍵となります。オウンドメディアは、特定のターゲット層を意識したコンテンツ制作が可能であり、より高い精度で顧客との接点を作れます。
たとえば、特定の業界や職種に特化した課題解決型の記事を掲載すれば、その課題を抱える読者層が自然に集まる仕組みを作れるでしょう。さらに、ターゲット層の顧客が求める情報を正確に提供すれば、より深い信頼関係を構築することが可能となります。こうしたターゲットを絞った戦略は、単なるトラフィックの増加を目的とするのではなく、顧客ニーズに応える高品質なコンテンツの提供を目指すものです。ターゲットとなる顧客が抱える課題に対し、適切なコンテンツを用意してSEO対策を行えば、効果的にアプローチできるでしょう。
ブランディングができる
オウンドメディアは、企業のブランド価値を高めるための強力なツールとしても機能します。特にBtoBビジネスでは、顧客に対する信頼感が取引成立の重要な要素となるため、オウンドメディアを活用しての自社の専門性やユニークな価値観の発信が極めて効果的です。
たとえば、自社の技術的な優位性や業界における成功事例を紹介する記事を掲載すれば、顧客に対して「この企業は信頼できる」「この分野のプロフェッショナルである」という印象を与えられるでしょう。さらに、独自性のある視点や切り口を持った記事を提供すれば、企業のブランドイメージを強化し、競合との差別化を図れます。
採用強化にもつながる
BtoB企業がオウンドメディアを活用する際、見逃してはならないのが採用活動への波及効果です。特にオウンドメディアでは、自社の文化や価値観、働き方を伝える記事を掲載でき、これが求職者に対する強力なアピールとなります。
たとえば、スタッフインタビューや具体的な業務内容を紹介する記事を通じて、求職者はその企業で働くイメージをより具体的に描けるでしょう。また、企業の透明性や成長性をアピールすれば、求職者に対する信頼感の醸成も可能です。このように、オウンドメディアは採用活動における「見える化」の役割を果たし、人材確保の重要なツールとなります。
コストが読みやすい
最後に、オウンドメディア運営はコスト面でも大きなメリットを持っています。広告とは異なり、短期的な予算消化型の施策ではなく、長期的に資産として残るコンテンツを蓄積できる点が特徴です。初期投資が必要ではあるものの、一度作成した記事やコンテンツは繰り返し活用が可能であり、ランニングコストを抑えつつ持続的な効果を期待できます。
さらに、オウンドメディアの運営はコストの透明性が高いため、事前に費用対効果を計算しやすいという利点もあります。これにより、企業は限られたリソースを効率的に活用し、戦略的なマーケティング活動の展開が可能となるでしょう。
BtoB企業がオウンドメディアを運営するデメリット
オウンドメディアは多くの利点を持つ一方で、運営にはさまざまな課題や困難が伴います。企業がオウンドメディアに取り組む際は、これらのデメリットを十分に理解し、適切な対策を講じる必要があります。
運営に手間がかかる
オウンドメディアの運営は、一見簡単に見えて実際は非常に労力を要するプロセスです。質の高いコンテンツを継続的に制作するには、専門的な知識を持つライターの確保、編集、校正、デザイン、さらには掲載後のメンテナンスなど、多岐にわたる作業が発生します。
特にBtoB領域では、より専門性の高いコンテンツが求められるため、単なる記事作成ではなく、深い業界理解と洞察力が必要となります。社内の専門家の時間を割く必要があり、通常の業務に支障をきたす可能性もあるでしょう。また、コンテンツの企画から制作、公開、分析、改善のサイクルを回すには、専任チームの設置や外部リソースの活用など、組織的な対応が不可欠となります。
SEOに関する知識やスキルが求められる
オウンドメディアを効果的に機能させるためには、高度なSEOスキルが求められます。単に記事を書くだけでなく、検索エンジンのアルゴリズムの理解、適切なキーワード選定、記事の構造化、メタ情報の最適化など、専門的な知識が必要です。
近年の検索エンジンは、単なるキーワードマッチングではなく、コンテンツの質や関連性、ユーザーエクスペリエンスを重視しています。そのため、技術的なSEOスキルだけでなく、ユーザーにとって真に価値のあるコンテンツを制作する能力が求められます。多くの企業では、このような高度なスキルを持つ人材の確保が困難であり、外部専門家への依存を余儀なくされるケースも少なくありません。
成果につながるまで時間がかかる
オウンドメディアの効果は、即効性のあるマーケティング手法とは異なり、長期的な視点で評価する必要があります。検索エンジンでの順位向上、ブランド認知の拡大、潜在顧客との信頼関係の構築には、通常数か月から1年以上の継続的な努力が求められるでしょう。
短期的な成果を求める経営層や関係者にとって、このタイムラグは大きな課題となり得ます。投資対効果を即座に示すことが難しく、経営資源の配分や継続的な予算確保に関して、社内調整が困難になる可能性があるでしょう。また、競合他社との差別化や独自の視点の確立には、さらに長い期間を要する場合があります。
BtoB企業のオウンドメディアを設計する流れ・手順
オウンドメディアの成功は、綿密な計画と戦略的アプローチによって実現されます。効果的なオウンドメディアを構築するためには、各段階で慎重かつ戦略的な意思決定が求められます。以下に、詳細な設計手順をご紹介します。
目的と目標を明確にする
オウンドメディア構築の出発点は、明確な目的意識です。単に情報を発信するだけでなく、具体的にどのような成果を得たいのかを徹底的に検討する必要があります。潜在顧客の獲得、ブランド認知度の向上、リード生成、顧客との関係構築など、目的は多岐にわたります。
これらの目的を設定する際は、経営層、マーケティング部門、営業部門など、社内の関係者と綿密な協議を重ねましょう。各部門の視点や期待を理解し、組織全体として整合性のある目標を設定すれば、オウンドメディアの戦略的な価値を最大化できます。
KPI(重要業績評価指標)の設定においては、定量的かつ具体的な数値目標を明確にしましょう。たとえば、月間のユニークユーザー数、リード獲得数、コンバージョン率、平均滞在時間、ページビュー数などを具体的な数値で設定し、進捗を継続的に測定します。
テーマを決める
オウンドメディアのテーマ選定は、企業の専門性と顧客のニーズを的確に反映する極めて重要なプロセスです。自社の強みや独自の視点、提供できる価値を中心に据えながら、ターゲット顧客が真に関心を持つテーマを設定しましょう。
テーマ選定のためには、徹底的な市場調査とベンチマーキングが不可欠です。競合他社のオウンドメディアを分析し、未開拓の領域や独自の視点を見出しましょう。業界のトレンド、テクノロジーの変化、顧客のニーズを常に注視し、タイムリーで意義のあるテーマを選択します。
また、テーマは単発的なものではなく、長期的な視点で継続的に価値を提供できる領域を選ぶことが重要です。たとえば、業界のデジタルトランスフォーメーション、持続可能なビジネスモデル、イノベーションマネジメントなど、深い洞察と継続的な情報提供が可能なテーマを選定します。
ターゲットを設定する
ターゲットの明確な定義は、オウンドメディアの成功を左右する最も重要な要素のひとつです。単なる人口統計学的なアプローチを超え、潜在顧客の本質的なニーズと課題を深く理解する必要があります。
具体的なターゲット設定においては、職種、役職、企業規模、業界だけでなく、より深い心理的・行動的側面を分析します。意思決定プロセス、情報収集の習慣、キャリアへの野心、技術的リテラシーなど、多角的な視点からペルソナを構築しましょう。
BtoB領域では、企業の購買意思決定は複数の関係者によって行われるため、各ステークホルダーに対応したきめ細かいアプローチが求められます。経営層、技術部門、現場責任者など、それぞれの関心事や課題に応じたコンテンツ戦略を立案する必要があります。
カスタマージャーニーマップを作成する
カスタマージャーニーマップは、顧客の購買プロセスにおける複雑な意思決定を可視化する戦略的ツールです。従来の単線的な購買プロセスではなく、より複雑で非線形的な顧客体験の詳細な分析が求められます。
BtoB領域における顧客ジャーニーは、特に複雑な様相を呈します。初期の問題認識から、解決策の探索、比較検討、意思決定、導入後のサポートまで、各ステージで顧客が直面する課題や感情を詳細に理解する必要があるでしょう。
このマップ作成においては、実際の顧客へのインタビューやアンケート、営業部門からのフィードバック、顧客サポート部門の知見を総合的に活用します。デジタルトラッキングツールによるデータ分析も、顧客行動の理解に大きく貢献するでしょう。
CMSを準備する
コンテンツマネジメントシステム(CMS)の選択は、オウンドメディアの運営効率と拡張性を左右する重要な決定です。単なる技術的な選択ではなく、長期的な戦略的視点から最適なプラットフォームを選定する必要があります。
選定においては、SEO対策機能、レスポンシブデザイン、セキュリティ、拡張性、カスタマイズ性などを総合的に評価します。WordPress、Drupal、Contentfulなど、それぞれのCMSの特徴を深く理解し、自社のニーズに最適なプラットフォームを選択しましょう。
同時に、コンテンツ制作から公開、分析までの一連のワークフローを効率化するツールの導入も重要です。統合的なマーケティングプラットフォームや、コラボレーションツールとの連携を考慮した選定が求められます。
コンテンツを作成する
コンテンツ制作は、オウンドメディアの最も重要な要素であり、単なる情報提供を超えた価値創造が求められます。ターゲット顧客の本質的な課題に対して、深い洞察と実践的なソリューションを提供するコンテンツが不可欠です。
コンテンツ制作では、多様なコンテンツ形式の活用も重要です。テキスト記事、ホワイトペーパー、インフォグラフィック、ウェビナー、ケーススタディ、インタビュー記事、技術解説など、ターゲットの情報収集スタイルに応じた柔軟なアプローチが求められます。
また、コンテンツ制作においては、社内の専門家や外部の有識者との協働が効果的です。単に情報を並べるのではなく、独自の視点や専門的な洞察を盛り込めば、差別化された価値を提供できます。常に最新の業界トレンドや技術動向を反映してコンテンツを更新していきましょう。
導線を設置する
効果的な導線設計は、オウンドメディアの最終目標であるコンバージョンを実現するための重要な戦略です。顧客が自然に次のアクションに進むよう、魅力的かつ戦略的なCTA(コールトゥアクション)を設計します。
導線設計においては、顧客のジャーニーステージに応じた適切な誘導が求められます。初期段階の読者には情報提供型のコンテンツ、検討段階の読者には詳細な技術解説や比較情報、意思決定段階の読者にはデモやトライアル申し込みなど、段階的なアプローチを取ります。
同時に、過度に押し付けがましくならないよう、顧客体験の自然な流れを意識しましょう。コンテンツの価値を最大限に活かしながら、サブスクリプション、資料ダウンロード、セミナー申し込みなど、顧客との継続的な関係構築につながる導線を設計します。
分析・改善を繰り返す
オウンドメディアの成功は、継続的な分析と改善プロセスによって実現されます。定量的データと定性的フィードバックを組み合わせた包括的な分析が求められます。Google Analytics、SEOツール、顧客フィードバックシステムなどを活用し、アクセス解析、ユーザー行動分析、コンバージョン分析を定期的に実施します。単なる数値分析にとどまらず、顧客の潜在的なニーズや課題の発見が重要です。
PDCAサイクルを継続的に回し、データに基づいたアプローチで常に最適化を図ります。コンテンツの質、SEO戦略、ユーザーエクスペリエンス、導線設計など、あらゆる側面において継続的な改善を行うことが、オウンドメディアの長期的な成功につながるでしょう。
BtoB企業のオウンドメディア成功事例
BtoB企業がオウンドメディアを運営することで得られる成果は、適切な戦略と実行力が伴えば非常に大きなものとなります。以下では、実際にオウンドメディアを成功に導いた代表的な事例を取り上げ、それぞれの企業がどのような工夫や取り組みを行ったのかを詳しくご紹介します。
経営ハッカー(freee株式会社)
経営ハッカーは、freee株式会社が運営する中小企業や個人事業主向けのオウンドメディアです。主に会計や経営に関する情報を発信し、freeeが提供するクラウド会計ソフトの利用を促進する役割を担っています。このメディアの特徴は、単に製品を売り込むのではなく、読者が直面する具体的な課題を解決するための実用的な情報を提供している点です。たとえば、「確定申告の手順」や労務管理、資金調達などが挙げられます。
経営ハッカーが成功した理由のひとつは、SEO対策に優れた記事制作を徹底していることです。適切なキーワードを設定し、ユーザーが求める情報に的確に応える記事を提供しているのが特徴です。また、記事内で自然な形でfreeeのサービスを紹介することで、顧客獲得に結びつける仕組みが構築されています。
Bizpedia(株式会社マネーフォワード)
Bizpediaは、株式会社マネーフォワードが運営するメディアであり、企業の経理や財務に関する情報を中心に発信しているメディアです。広範囲にわたるテーマを取り扱っており、経理担当者から経営者まで幅広いターゲット層にアプローチしています。特に、業務効率化やITツールの活用に関する具体的なノウハウを提供する記事が人気を集めています。
Bizpediaの成功要因として挙げられるのは、定期的なコンテンツ更新や質の高い情報発信です。さらに、記事内にマネーフォワードのサービスやソリューションを紹介するリンクを設置し、訪問者を見込み客へと転換していく仕組みを整えています。
サイボウズ式(サイボウズ株式会社)
サイボウズ式は、サイボウズ株式会社が運営するオウンドメディアです。チームワークや働き方改革をテーマにした情報を発信しています。このメディアのユニークな点は、企業が提供する製品に直接的に結びつくテーマだけでなく、働く人々の価値観や多様性に関する話題も取り上げているところです。
たとえば、「働き方の選択肢を広げる重要性」や「組織内コミュニケーションの改善」といったテーマは、単なる製品紹介以上の価値を提供しています。これにより、読者の共感を生み出し、サイボウズのブランドイメージを向上させているといえるでしょう。
HubSpot 日本公式ブログ(HubSpot Japan 株式会社)
HubSpot 日本公式ブログは、マーケティングオートメーションやCRMの導入に関する記事が中心です。特に中小企業やマーケティング担当者に向けた実践的なノウハウが豊富に掲載されています。デジタルマーケティングの最新トレンド、戦略、活用法など、実用的なテーマの記事が記載されています。
このメディアの強みは、HubSpot自体がインバウンドマーケティングのリーダー企業であることを活かしている点です。自身のツールを用いた具体的なマーケティング戦略を紹介し、実績に基づいた説得力のあるコンテンツを提供しています。また、記事を通じてHubSpotの無料ツールや資料のダウンロードを促進する導線を設置しており、効果的にリードを獲得しています。
マーキング学習塾(株式会社キーエンス)
株式会社キーエンスが運営するマーキング学習塾は、製造業界に特化したマーケティング情報を主に提供しているメディアです。このメディアは、非常にニッチな分野に焦点を当てており、業界内での認知拡大やブランディングなどを目的としています。
マーキング学習塾が成功したポイントは、その専門性の高さにあります。他の一般的なメディアでは取り上げられないような技術的に深い内容をわかりやすく解説し、ターゲット層からの信頼を獲得しています。また、記事の中でキーエンスの製品を効果的に紹介し、読者が具体的な製品導入を検討する際の選択肢として意識させる構成となっています。
mercan(株式会社メルカリ)
株式会社メルカリが運営するmercanは、メルカリに関する専門知識や最新トレンドを伝えるメディアです。このメディアの特徴は、社員インタビューやプロジェクト事例を中心に、自社の価値観や働きがいを伝えるコンテンツを発信している点です。
実際にメルカリが行っている事業開発やマーケティングに関する情報を発信し、読者に価値を提供しています。
ばね探訪(東海バネ工業株式会社)
ばね探訪は、東海バネ工業株式会社が運営するメディアです。主にばねに関する専門知識や活用事例を発信しています。このメディアは、一見すると地味なテーマであるばねを、興味深く感じさせる工夫が随所に施されています。
たとえば、ばねの構造や特性を科学的に解説する記事は、エンジニアや設計者にとって非常に実用的です。また、具体的な製品事例や導入事例を通じて、自社製品の魅力を効果的に伝えています。ばね探訪は、ニッチな分野における専門性と顧客ニーズへの深い理解を武器に、安定した成果を上げています。
BtoB企業がオウンドメディアを運営する際のよくある失敗例
BtoB企業がオウンドメディアを運営する際、成功事例と同じくらい重要なのが失敗事例を学ぶことです。成功の裏には、多くの試行錯誤が存在します。ここでは、BtoB企業が陥りやすいオウンドメディア運営の失敗例を取り上げ、その原因と対策についてご紹介します。
SEOの知識が不十分、古い
オウンドメディア運営において、SEOの知識が不十分であったり、古い情報をもとにした戦略が使われていたりしている場合、検索エンジンでの評価が低下し、訪問者数が伸び悩むケースがあります。SEOは、検索エンジンのアルゴリズムが頻繁に更新されるため、最新のトレンドや技術に基づいて運用しなければなりません。しかし、運営側が十分な専門知識を持っていなかったり、外部の専門家に相談せずに進めてしまうと、たとえばキーワードの選定が不適切だったり、モバイル対応が不十分だったりと、結果的に大きな機会損失を招く場合があります。
効果計測ができていない
オウンドメディアの効果を正確に計測していない点も、よくある失敗例のひとつです。たとえば、Google Analyticsやサードパーティツールを導入していても、どの指標に注目すべきかがわからず、ただ漠然とPVやUU(ユニークユーザー)の数値だけを追いかけてしまうケースが見受けられます。
オウンドメディア運用の際は、KPIを明確に設定し、それに基づいて適切なデータを収集・分析しましょう。これを怠ると、何が成功の要因であり、何が課題なのかを正確に把握できず、改善の方向性を見失う原因となります。
セッション数が少なく、効果検証がしづらい
オウンドメディアを立ち上げたものの、セッション数が少ない状態が続く場合、十分なデータが集まらず、効果検証が難しくなる場合があります。この原因として考えられるのは、ターゲット層に適したコンテンツが提供されていない、または、SEO対策や広告宣伝が不十分であるなどです。オウンドメディアをはじめたばかりの段階では、検索エンジンやSNSなどでの露出を強化する戦略が必要です。これを怠ると、訪問者数を増やすのに非常に長い時間がかかるでしょう。
継続的なコンテンツの追加・リライトができていない
多くの企業がオウンドメディアを立ち上げる際に直面する課題として、継続的なコンテンツの追加やリライトができていない場合が挙げられます。コンテンツ制作には多くの時間と労力が必要であり、特に企業のリソースが限られている場合、これが原因で更新が滞るケースがあります。また、過去のコンテンツを適切にリライトし、検索エンジンや読者のニーズに合った内容にアップデートしないと、コンテンツが陳腐化し、アクセス数が減少してしまいます。特にBtoB領域では、専門性の高い情報が求められるため、常に最新かつ信頼性のある情報を提供し続けることが重要です。
コンテンツの量はあるが質が低い
コンテンツの量を重視するあまり、質が伴わない状態になる点も、BtoB企業が陥りやすい失敗のひとつです。検索エンジンの評価を上げるために多くの記事を公開しようとするあまり、それぞれの記事がターゲットにとって有益でなかったり、十分な専門性や深さが欠けたりしている場合、結果的にメディア全体の評価を下げてしまう場合があります。
特にBtoBでは、ターゲット層が専門的な知識を持つ読者である場合が多く、表面的な内容や信頼性の低い情報では満足されません。したがって、量だけでなく質にも重点を置くことが求められます。
アクセス数は増えたが成果につながらない
アクセス数が増加しているにもかかわらず、具体的な成果(たとえばリードの獲得や契約の締結)につながらないという事例も少なくありません。これは、訪問者が求める情報と提供されているコンテンツが一致していない、あるいは、コンテンツ内の導線が適切でないことが原因の場合もあります。
オウンドメディアの役割は単に訪問者を集めるだけでなく、次のアクション(たとえば問い合わせや資料請求)につなげることです。そのため、コンテンツ制作時には、明確なゴールを設定し、それを達成するための導線設計を徹底する必要があります。
短期的な成果を求めてしまう
オウンドメディアは長期的な取り組みで成果を出すものですが、短期的な成果を求めてしまい失敗するケースもあります。たとえば、数か月で目に見える成果が出ないために焦り、運営を中断してしまう場合があります。しかし、SEOやブランド認知の向上には時間がかかるため、短期的な視点だけで評価してしまうと投資が無駄になってしまうでしょう。成功しているオウンドメディアの多くは、長期的な戦略を持ち、数年単位で改善を続ける姿勢を持っています。
BtoB企業のオウンドメディア運営におけるポイントとは
BtoB企業がオウンドメディアを成功させるためには、明確な戦略を持ち、適切な運営を行うことが重要です。オウンドメディアの運営には多くの労力と時間が必要ですが、事前に正しい方向性を設定し、運営体制を整えれば、効率的かつ効果的に成果を上げられるでしょう。
ここでは、運営を成功に導くための具体的なポイントを解説します。フェーズごとの目標設定、適切な運営体制の構築、そしてツールの活用という三つの側面に焦点を当てながら、それぞれの重要性と実践方法を見ていきます。
フェーズに合わせたKPIを設定する
オウンドメディアを運営する際、最初に取り組むべきなのが、フェーズごとの適切なKPI(重要業績評価指標)の設定です。多くの企業が陥りがちな失敗として、最初から大きな成果を求めてしまう場合があります。しかし、オウンドメディアは短期的な成果よりも、長期的な視点での評価が求められます。そのため、運営の各フェーズに応じたKPIを設定し、それを段階的に達成していくことで最終的なゴールに近づけていくアプローチが重要です。
たとえば、立ち上げ初期のフェーズでは、コンテンツ数の増加や検索エンジンでのインデックス数、PV(ページビュー)数をKPIとして設定することが一般的です。この段階では、まず訪問者を増やすための基盤作りを優先します。そして、中期フェーズに移行すると、リード獲得やエンゲージメントの向上を目的とした指標、たとえば資料請求数やメルマガ登録者数を追いかけるようになります。最終的には、契約締結や売上向上といった具体的なビジネス成果をKPIとして設定します。
このようにフェーズに応じて指標を変えれば、無理のない形で目標を達成しつつ、メディア運営の進捗の正確な把握が可能になります。また、KPIは常に運営状況や市場環境に合わせて見直しを行うべきです。データをもとにした柔軟な目標設定が、オウンドメディアの成功を左右する大きな要因となります。
運営体制を整える
次に重要なのが、オウンドメディア運営のための体制を整えることです。これは、組織内に専門的な知識を持つ人材を配置するだけでなく、運営のためのプロセスや責任分担の明確化も含みます。特にBtoB企業においては、扱うテーマが専門的であるケースが多いため、コンテンツ制作には高度な知識やスキルが必要です。したがって、社内のリソースを適切に活用しながら、必要に応じて外部の専門家や制作会社との連携を検討することが求められます。
また、担当者だけに運営を任せるのではなく、経営陣や他部門との連携強化も重要です。たとえば、営業チームやマーケティングチームと情報を共有し、顧客のニーズや市場動向をコンテンツに反映させれば、よりターゲットに響くメディア運営が可能になります。さらに、運営体制を整える際には、責任範囲を明確にし、定期的な進捗管理やレビューを行う仕組みの導入が効果的です。
特に中長期的な視点で運営を行う場合、リソースの確保と管理は大きな課題となります。オウンドメディア運営を専任で行うチームを設置するか、既存のスタッフに業務を分担させるかを判断する際には、コストと効果のバランスを考慮しながら進める必要があります。このように、明確な役割分担と連携体制を築けば、安定した運営の基盤となるでしょう。
ツールを活用する
オウンドメディア運営を効率化し、より高い成果を上げるためには、適切なツールの活用が欠かせません。現代のデジタルマーケティングでは、多種多様なツールが利用可能であり、それらを活用すれば運営の負担を軽減しつつ、パフォーマンスの最大化が可能です。
たとえば、コンテンツ管理システム(CMS)を活用すれば、記事の作成や編集、公開が容易になります。特に中小規模の企業では、WordPressのような手軽でカスタマイズ性の高いCMSが広く利用されています。また、SEO対策ツールを使うことで、キーワードの選定や競合分析、サイトの改善ポイントを効率的に把握できます。これにより、検索エンジンでの評価を向上させ、訪問者数を増やせるでしょう。
さらに、メールマーケティングツールやポップアップ機能を持つツールを活用すれば、訪問者との接点を増やせます。たとえば、サイト内にメルマガ会員登録の導線を設置し、訪問者に定期的に情報を提供する仕組みを構築すれば、リード獲得の効率を高められるでしょう。また、配配メールのようなポップアップ機能を導入すれば、訪問者を取りこぼさず、効果的にアプローチできる仕組みを整えられます。
加えて、分析ツールを活用すれば、運営の成果を可視化し、次の施策に活かせるようになるでしょう。Google Analyticsをはじめとする解析ツールを使えば、訪問者の行動やコンテンツの効果を詳細に把握できます。これをもとに、改善ポイントを特定し、より効果的な施策を展開できます。
ツールの選定においては、自社の課題や目標に応じたものを選びましょう。必要以上に多くのツールを導入するのではなく、運営の目的に合ったものを適切に使いこなせば、コストを抑えつつ効果的な運営を実現できます。
まとめ
オウンドメディアは、BtoB企業にとって見込み客の獲得や認知度向上、ブランディング強化など多くのメリットをもたらします。一方で、運営には専門知識や労力が求められ、成果が表れるまで時間を要することから、慎重な計画と実行が必要です。成功するためには、明確な目的とKPI設定、適切な運営体制の構築、そして効率的なツール活用が欠かせません。過去の事例から学び、自社のターゲットに合った戦略を練りましょう。また、失敗例を踏まえた継続的な改善と、長期的な視点を持った取り組みが、メディアの価値を最大化する鍵となるでしょう。

商談獲得に特化した「配配メールBridge」は、初心者でも簡単に新規顧客開拓を始められるMAプランです。
シンプルな設定画面と専門知識不要の操作で、誰でもすぐに使い始められます。さらに、専任担当による無償の導入活用支援や、充実のアフターフォローで、安心してご導入いただけます。
導入企業様の成功事例や改善要望を活かし、常にアップデートしていくことで、お客様の成果最大化に貢献いたします。