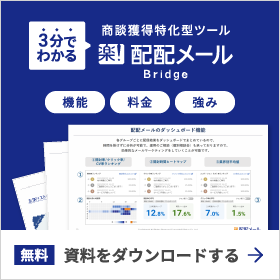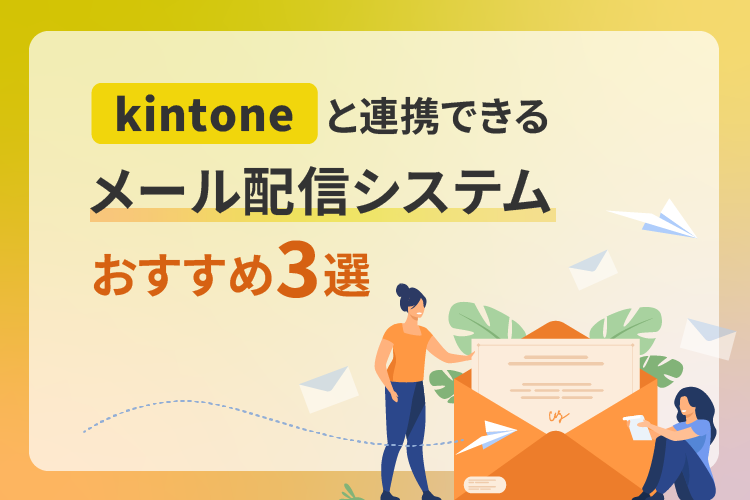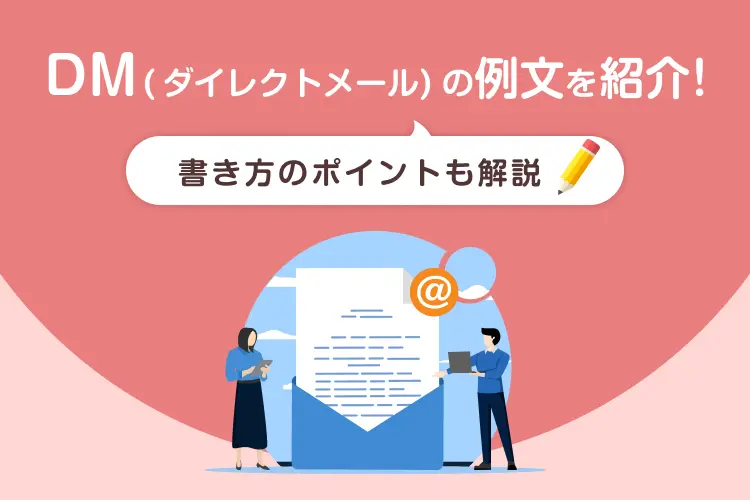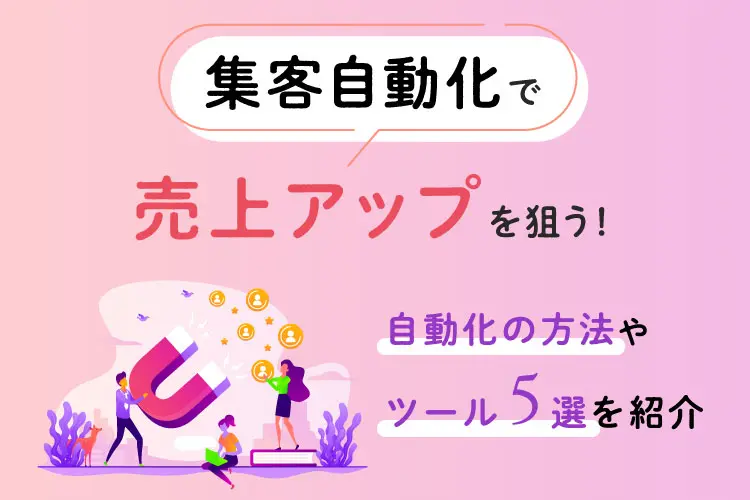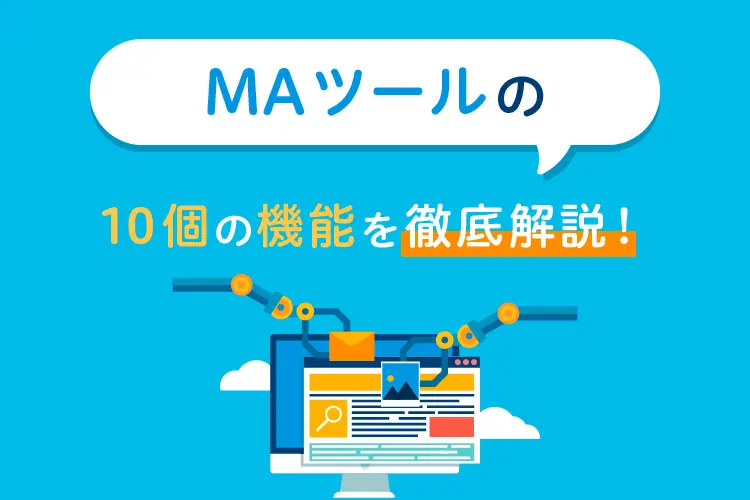営業の掘り起こしとは?休眠顧客から案件創出する方法やコツについて解説
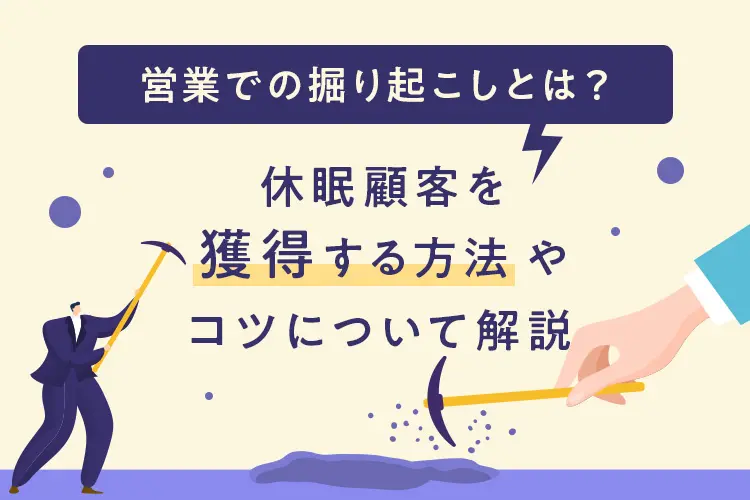
一度問い合わせや商談をしたものの購入にいたらなかった休眠顧客は、再度アプローチする掘り起こしを行うことが大切です。ただ忘れているだけの顧客も多く、アプローチにより効率的に顧客を増やすことができます。
ここでは、掘り起こしの重要性や休眠顧客が発生する理由、掘り起こしの方法などを紹介します。
「新規契約を生み出す休眠顧客への営業ノウハウ」 資料をダウンロード
目次
休眠顧客とは
休眠顧客とは、過去に自社と取引や商談があったものの、 一定期間以上接点のない顧客のことを指します。具体的な期間は業種や企業によって異なりますが、1年〜3年接点がない顧客を休眠顧客と定義することが多いです。
見込み客・潜在顧客・顕在顧客の違い
顧客のフェーズによって名称が異なるため、それぞれの違いについても理解しておきましょう。
見込み客
見込み客とは、自社の商品やサービスに関心があり、将来的に導入・購入する可能性が高い顧客のことを指します。
潜在顧客
潜在顧客とは、自社の商品やサービスに興味を持っている可能性が高いが、まだ導入・購入には至っていない顧客のことを指します。
顕在顧客
顕在顧客とは、自社の商品やサービスを認識し、導入・購入を比較検討している顧客のことを指します。
なぜ休眠顧客の掘り起こしが重要なのか
ではなぜ休眠顧客の掘り起こしが重要なのでしょうか。ここでは、2つの理由をご紹介します。
市場の成熟
日本市場は成熟期を迎え、多くの業界で新規顧客の獲得が困難になっています。人口減少や競争激化により、新規顧客の獲得コストは年々上昇傾向にあります。このような環境下では、すでに取引実績のある休眠顧客への再アプローチが効率的な営業戦略として注目されているのです。
市場の成熟化に伴い、製品やサービスの差別化が難しくなることで、新規顧客の獲得においては、より多くの時間と労力、そして費用を投じることになります。一方で、休眠顧客はすでにあなたの企業や製品について基本的な理解があり、信頼関係も構築できている可能性が高く、再度の取引開始までのハードルが比較的低いと言えるでしょう。
低コスト
休眠顧客へのアプローチは、新規顧客開拓と比較して大きなコストメリットがあります。新規顧客獲得には、認知向上のための広告費用、営業スタッフの人件費、商談にかかる時間的コストなど、多大なリソースが必要です。
一方、休眠顧客に対しては、すでに基本的な情報や取引履歴が存在しているため、効率的なアプローチが可能です。過去の取引データを活用すれば、顧客のニーズや課題を予測し、的確な提案を行えます。また、信頼関係が構築されているため、商談までのプロセス短縮も可能です。
休眠顧客が発生する理由
休眠顧客が発生するのは、BtoCとBtoBで共通する理由として商品・サービスが不要になった、価格やスペックがニーズに合っていないということがあげられます。
BtoBではさらに、検討に時間がかかっているケースが考えられます。
ここでは、休眠顧客が発生する理由を詳しくみていきましょう。
商品が不要になった
顧客側の状況が変化して商品・サービスを利用する必要がなくなるケースがあります。
BtoBでは、予算の変更や社内環境の変化などで、一旦検討がなくなるというケースも考えられるでしょう。
このような顧客側の事情による休眠の場合は、すぐに検討が再度始まることは少ないため、中長期的にアプローチして、再度検討が始まったタイミングを検知するようにしておくことが重要です。
商品の価格やスペックに課題がある
商品・サービスの価格あるいはスペックが顧客のイメージやニーズに合わず、休眠顧客になるケースもあります。
一度商品・サービスがニーズに合わないと判断されると、掘り起こしは難しくなります。イメージやニーズに合わない原因を究明することが必要です。
商品・サービス自体に問題はなくても、担当者の対応やアフターフォローの不足が原因で休眠顧客になる場合もあります。
課題がそのままでは、顧客の掘り起こしはできません。まずは課題を見つけて分析し、解決することが必要になるでしょう。
検討に時間がかかっている
BtoB特有の理由として、購入までの検討期間が長いという理由があげられます。商品・サービスの利用には決裁者の承認を得る必要があり、決定までの検討期間が長くなって最終的に見送られるケースもあります。
連絡がないからとフォローもせず放置してしまうと、競合他社で契約されてしまう可能性もあります。
検討において必要な情報を提供するなど、定期的に連絡を取りフォローするようにしましょう。
忘れられている
顧客の記憶から企業が完全に忘れ去られているケースも挙げられます。一度取引があった顧客であっても、その後の継続的なコミュニケーションや情報発信が不足していると、顧客の意識から徐々に企業の存在が薄れていきます。特に商品やサービスの購入サイクルが長い場合、次回の購入を検討する時期が来ても、以前取引のあった企業名やスタッフの名前を思い出せないことが多々あるでしょう。
このような状況は、競合他社による積極的なアプローチや新規参入企業の台頭により、さらに加速される傾向にあります。顧客は日々さまざまな企業からの情報に触れており、過去の取引先との記憶は、新しい情報によって上書きされていきます。そのため、定期的な接点を持たない企業は、顧客の選択肢から自然と外れてしまう結果となっているのです。
休眠顧客を掘り起こす5つの手法
休眠顧客の掘り起こしには、主に以下のような5つの手法があります。
- メールを送る
- DM(ダイレクトメール)を送る
- 架電(テレアポ)する
- CRMやSFAを活用する
- SNSを活用する
それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の状況に合わせて選ぶとよいでしょう。
CRMやSFAなどのツールを活用するのもおすすめです。
休眠顧客を掘り起こす方法について、それぞれ解説します。
1.メールを送る
メールは、少ない工数と低コストで実施できるマーケティング手法です。送信後の効果測定が容易であり、改善につなげやすいというメリットがあります。
メールはただ手当たり次第に送るのではなく、顧客を分類してそれぞれに合わせたメールを送ることが大切なポイントです。休眠状態になった理由は「予算が合わなかった」「十分に関心を高められなかった」などさまざまです。それらの理由に合わせ、アプローチの内容も変わってきます。
メールの手法を成功させるには、相手の関心を高めるための工夫が必要です。その際に意識するポイントは以下の3つがあげられます。
- 具体的な数字を挙げる
- ベネフィットを提示する
- 商品・サービスのメリットを伝える
数字のデータを使って信憑性を高め、自社の商品・サービスを利用することでどのような利益を得られるのかを提示します。さらに、自社の商品・サービスを利用するメリットを伝えましょう。
関連記事はこちら休眠顧客を発掘するメールの書き方を徹底解説
2.DM(ダイレクトメール)を送る
DM(ダイレクトメール)は、パンフレットやチラシを郵送するアプローチです。
封書やはがきのデザインを工夫することで開封率が高まります。
ターゲットを絞り、相手に合わせたデザイン・文面にすることで、掘り起こしの効果を高めることが可能です。割引券やサンプルなどを入れ、より興味を惹くこともできます。
DMは手元に残るため、保存してあとから検討してもらいやすいのもメリットといえるでしょう。
ただし、DMはメールに比べて手間とコストがかかります。そのため、ターゲットの設定を適切に行い、精度を高めた戦略が必要です。
関連記事はこちらDM営業とは?効果を上げるコツやメリット・デメリットなどを簡単に解説
3.架電(テレアポ)する
電話は顧客と直接会話するため、顧客の知りたいことにリアルタイムで回答もできるので、商品・サービスへの関心を呼び起こしやすい方法です。休眠顧客の掘り起こしに効果的といえるでしょう。
文章では伝えきれないことがある場合、電話であればより説得力のある訴求ができます。既に一度は関係性を持った顧客であり、新規顧客への架電よりもハードルは低いといえるでしょう。
一人ひとりに電話することは人件費やコストがかかりますが、相手に合わせた案内ができるのはメリットです。再度の利用にはいたらなかった場合でも、会話を通して商品・サービスに関するフィードバックを得られます。今後の休眠顧客の掘り起こしに役立てることができるでしょう。
また、電話は稼働がかかりすぎて実施できないという場合は、メールを活用するのがおすすめです。
メールに反応があった顧客はサービスや商品に興味があるということなので、反応があった顧客に絞ってテレアポすることで、稼働を削減して実施できます。
例えば、配配メールBridgeの「ホットリード抽出機能」を活用すれば、複数の配信結果を横断して、どれだけの回数の開封/クリックを行ったかで反応顧客を抽出できます。より精度の高いホットリードにのみアプローチできるようになるため、架電効率が飛躍的に向上します。
関連記事はこちらテレアポを成功させるコツとは?事前準備やトークの極意を解説
4.CRMやSFAを活用する
休眠顧客ごとに適したアプローチするには、顧客情報の適切な管理が求められます。そのために役立つのが、顧客管理ツールのCRMやSFAです。
CRMとは「Customer Relationship Management」の略で、顧客との関係性を管理するツールです。顧客の氏名や年齢、属性などの基本情報をはじめ、購買履歴など顧客に関する情報を一元管理します。CRMで蓄積した情報をもとにマーケティングを行うことで、高い効果が期待できます。
SFAとは「Sales Force Automation」の略で、「営業支援システム」のことです。営業の情報と業務プロセスを自動化し、営業活動で管理する情報全般をデータ化して蓄積・分析できるシステムです。営業活動のプロセスや進捗状況、顧客との関わり方などを可視化できます。可視化により顧客情報や進捗状況をリアルタイムで把握でき、売上予測やデータの分析、フィードバックなど幅広く活用できるツールです。
CRMで顧客情報の管理を行うことで、なぜ休眠したのか、検討のみで終わってしまったのかといった理由を見極めることができます。
掘り起こしの際は、休眠顧客のデータを抽出し、顧客の状況や営業活動の詳細な状況を分析することが重要です。分析結果から、より効率的なアプローチ方法を見つけることができるでしょう。
関連記事はこちらMA・CRMは何が違う?取り組む前に理解を深めよう
5.SNSを活用する
現代のビジネスコミュニケーションにおいて、SNSは重要なチャネルとなっています。特にLINE公式アカウントは、直接的かつパーソナルなコミュニケーションを可能にする強力なツールです。LINE公式アカウントを活用することで、従来のメールマーケティングでは実現できなかった、高い開封率と即時性のあるコミュニケーションを実現可能です。また、活用方法次第では、一方的な情報発信だけでなく、双方向のコミュニケーションが取れる点も利点と言えます。
企業からの情報発信においては、ターゲットを絞った効果的な情報提供が可能となり、クーポンや特別オファーの配信も高い効果を発揮します。顧客との関係性を維持・強化するためには、定期的な情報発信や特別キャンペーンの案内など、顧客にとって価値のある情報提供を継続的に行うことが重要です。さらに、顧客の反応や行動データを分析すれば、より効果的なコミュニケーション戦略を構築できます。
加えて、顧客の記憶にも残りやすくなる副次的なメリットにも期待できるでしょう。
効率良く掘り起こしに成功した事例
休眠顧客の掘り起こしにおいて、実際に成功を収めている企業の事例を見ると、効果的なアプローチ方法が見えてきます。以下では、特に効率的な成果を上げた事例とその分析手法について詳しく解説します。
メール配信後、反応者にテレアポ
ある事例では、顧客に対して、段階的なアプローチを実施し、高い成果を上げました。まず全休眠顧客にメールを配信し、開封やリンクのクリックなどの反応データを収集します。その後、反応のあった顧客に対して優先的にテレアポを実施するという方法を取りました。この方法により、ランダムなテレアポと比較して、商談化率が向上したという結果が得られたそうです。
2通のメールの反応者にテレアポ
さらに進んだアプローチとして、2回以上のメール配信を行い、継続的に反応を示した顧客に絞ってテレアポを行う手法も効果を上げています。ある事例では、1通目でコラムを発信し、そのURLからアクセスした顧客だけに2通目を送信しました。2通目のメールには、無料トライアルや資料の案内など具体的な提案を行うという段階的なアプローチを実施しています。両方のメールに反応した顧客に対してテレアポを行った結果、アポイント獲得率が向上し、最終的な成約率も大きく改善されました。
顧客の反応に応じてメールを分ける
ある事例では、顧客の反応パターンに応じて異なるメッセージを配信する戦略を採用し、大きな成果を上げています。初回メールの開封有無、リンクのクリック状況、資料請求の有無などに応じて、次のアプローチ内容を変えていくことで、より効果的なコミュニケーションを実現しました。
例えば、メール配信への興味が高い顧客へは営業活動でのメール配信のコラムを送信し、それをクリックした人にはトライアルを訴求します。メール配信への興味が低い顧客へは、営業活動全般のコラムを配信し、それをクリックした人には資料を訴求します。そして反応した人にテレアポを行いました。グループ分けを行うことで、さらにアポイント獲得率が上昇したそうです。
掘り起こしを成功に導くコツ

休眠顧客の掘り起こしを成功させるには、継続的なアプローチと休眠状態になった理由の把握が大切です。休眠の理由はさまざまあるため、しっかり分析してアプローチする休眠顧客を見極めなければなりません。顧客ごとに適切なアプローチをすることも重要です。
ここでは、掘り起こしを成功させるコツについて詳しくみていきましょう。
継続的にアプローチする
休眠顧客の掘り起こしは、継続的なアプローチが大切です。休眠した顧客の多くは、数年以内に他社で商品・サービスを購入しているというデータがあります。
顧客のニーズが再び高まるタイミングを逃さないよう、定期的なアプローチを継続的に行いましょう。メールであれば簡単にできるため、定期的にアプローチをすることに負担はありません。
関連記事はこちらメールリードナーチャリングの効果的な6つの手法と成功事例
なぜ休眠状態になったのかを理解する
休眠顧客となった背景には、そもそもニーズがなくなった、予算やスペックが合わない、検討に時間がかかっているなど、さまざまなことが考えられます。
背景にどのような理由があるのかによって、フォローやアプローチの仕方も変わりますので、まずはどういった要因で休眠顧客となっているのかを調査するようにしましょう。
アプローチするべき休眠顧客を見極める
前述の通り、休眠顧客となった理由はさまざまです。休眠理由によって購入や契約するまでにかかる期間は変わります。優先的にアプローチすべき休眠顧客を見極め、ターゲットを絞りましょう。
例えば、そもそもサービスや商品の導入検討がなくなった場合は、いつまたニーズが再浮上するかわかりません。こういった場合は、関係の維持を目的に定期的にメールでお役立ち情報を提供するなど、できるだけ稼働を抑えてアプローチするのが良いでしょう。
一方で、検討に時間を要している場合は、検討が進めば契約や購入にいたりやすいので、検討を進める上で相手がどのような情報を必要としているかを調査し、メールや電話などでフォローするのが良いでしょう。
顧客ごとにアプローチを最適化する
自社の商品・サービスや休眠顧客の状況により、適切なアプローチ方法は異なります。顧客ごとにアプローチを最適化しましょう。
顧客の状況ごとのアプローチについて、一例は以下のとおりです。
- 予算に見合わない:キャンペーンや割引の案内をする
- 検討が長期化している:検討を進める上で必要な情報を提供する
- ニーズと合わないため休眠している:関連する別の商品・サービスを案内する
これはあくまで一例です。顧客の属性や休眠理由から、最適なアプローチを考えましょう。
顧客情報の管理精度を高める
休眠顧客の掘り起こしを効率的に行うには、適切な顧客情報の管理が求められます。休眠理由の分析や適切なアプローチを考える上で、顧客情報の管理精度を高めなければなりません。
効果的に休眠顧客の掘り起こしを行う際は、CRMやSFAを活用するのがおすすめです。顧客情報は常に最新の状態に保ち、顧客との対応履歴を記録するなど適切な管理を行いましょう。
関連記事はこちら営業支援ツールのメリットやおすすめツール10選を紹介
掘り起こしメールを送るなら「配配メールBridge」がおすすめ

配配メールBridgeは、メールマーケティングサービス「配配メール」に新規開拓や商談獲得に役立つ機能を搭載したMAプランです。
メール配信ツールからMAツールの架け橋としてご利用いただけ、MA導入の難易度にハードルを感じるものの、単なるメルマガの一斉配信から脱却したいという方にぴったりのプランです。
ステップメール、セグメント配信など基本機能はもちろんのこと、メールへの反応回数などから温度感の高い見込み客を可視化する「ホットリード抽出機能」や、メールの開封・クリック情報やWebサイトの特定ページを誰が訪問したかを通知する「来訪通知機能」により、ニーズが高まった見込み客に対して効率的に架電や追客メールを実施することができるようになります。
掘り起こしに役立つ「配配メールBridge」の機能
ホットリード抽出機能
ホットリード抽出機能は、見込み客リストへの過去のメール配信履歴から、メールへの反応回数により温度感の高い見込み客を可視化できる機能です。
たとえば、「3ヵ月以内に5回以上メールを開封」や「特定期間内にメール内のURLを3回クリック」などの条件で見込み客を抽出することができます。
メール1通ずつの開封履歴は確認できても複数のメールを横断的に分析できる機能は他のツールにはないことが多いため、特長的な機能となっています。
来訪通知機能
来訪通知機能は、リード情報を取得済みの休眠顧客がサイトを訪問した際に、リアルタイムで営業担当にメールで通知を飛ばすことができる機能です。サイト訪問をトリガーとして自動で追客メールを送ることも可能です。
顧客の検討度が高まったタイミングを検知することができるため、単なるテレアポとは違い商談につながりやすい見込み客に架電できるようになります。
まとめ
休眠顧客は、過去に接点のある顧客であり、その掘り起こしは新規顧客を開拓するよりも効率的です。市場の成熟により新規顧客の獲得が難しくなっている時代に、休眠顧客の掘り起こしは重要な戦略といえるでしょう。
掘り起こしの際は、確度の高い顧客を見極め、優先順位をつけることも大切です。アプローチにはさまざまな手法があるため、休眠理由や顧客の属性などで適切な手法を選ぶようにしましょう。

商談獲得に特化した「配配メールBridge」は、初心者でも簡単に新規顧客開拓を始められるMAプランです。
シンプルな設定画面と専門知識不要の操作で、誰でもすぐに使い始められます。さらに、専任担当による無償の導入活用支援や、充実のアフターフォローで、安心してご導入いただけます。
導入企業様の成功事例や改善要望を活かし、常にアップデートしていくことで、お客様の成果最大化に貢献いたします。